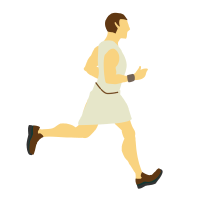フィボナッチ数列の無限和の解説をする前に
数学の分野でフィボナッチ数列の無限和が-1とされることはよく知られている話ですが、これは解析接続をした場合の話です。
一方で解析接続を一切せずに、「フィボナッチ数列の無限和が-1」であることをまるで証明できるかのような情報が、ネット上の数学系コンテンツでしばしば見受けられ、解析接続がよくわからない人はそれが正しいと思ってしまいます。しかし、実際はその証明方法では、正しい証明とはいえないのではないか、という内容について、今回解説させていただきます。
そのため、この話を正しく理解するために、まずは、フィボナッチ数列とは何かについて解説します。
その次に、フィボナッチ数列の無限和が-1になることについて、「解析接続を用いた証明方法」と、「解析接続を用いない、ネットでよく知られている証明方法」について解説します。
この後者の「解析接続を用いないバージョンの証明方法」は、YoutubeやHP上のネット上でよくフィボナッチ数列の証明方法として見受けられ、「解析接続はこんなに簡単に証明できる!」あるいは「実は数列の無限和は-1だった!」など、大げさに解説されています。
しかし、私個人の意見として、上記の後者の「解析接続を用いないバージョンの証明方法」ではおそらく根本から間違っているのではないか、という疑問を呈したいと思います。
※Youtubeでも解説しております。ここの情報より図解が多い解説なので、ぜひご覧ください。詳しくはページの下部にてご案内しております。
フィボナッチ数列
\(初期値:a_0=0 a_1=1\)
\(a_{n+2}=a_n+a_{n+1} (n\geq0) \)
フィボナッチ数列とは、初期値として\(a_0\)を0、\(a_1\)を1とし、\(a_{n+2}=a_n+a_{n+1}\)の漸化式で表したものです。
この漸化式にて、nは0以上の数字という条件があります。
このフィボナッチ数列を具体的に計算すると、0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… と限りなく続く数列になります。
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
試しに、\(a_{n+2}=a_n+a_{n+1} (n\geq0) \)の漸化式の部分を確認してみましょう。
0+1=1、1+1=2、1+2=3、2+3=5、3+5=8、5+8=13ですね。しっかりと、漸化式の結果と一致しましたね。
このようにして、フィボナッチ数列は無限に続く数列なのです。
フィボナッチ数列の無限和
さて、ここでフィボナッチ数列の無限和を求めてみましょう。具体的には、0+1+1+2+3+5+… とどこまでも足し算をします。これが、フィボナッチ数列の無限和です。
この無限和は、当然のことながら無限大に発散します。
0+1+1+2+3+5+8+13… = ∞ ①
しかし、解析接続という特別な条件の元では、これが-1になってしまいます。
0+1+1+2+3+5+8+13… = -1 ②
解析接続とは、元々の式を複素関数までに対応できるように、範囲を拡張したもので、厳密な意味では上側の解析接続なしの式とは違うものです。
なので、イコールで結ばれているからといって、解析接続された場合とそうでない場合とでは、式の意味が違うのです。
具体的にいえば、解析接続された場合、元の式ではなく、この場合では、複素平面まで拡張された\(F(z)=\frac{z}{1-z-z^2}\)の関数に、1を代入した結果\(F(1)\)を意味しています。
それがこの②の式に隠れているわけです。
解析接続であれば結果は-1ですが、解析接続でなければ当然ながら無限大に発散します。
これを、解析接続という前提条件を一切つけずに、「フォボナッチ数列の無限和は実は-1だった」とするのは間違いといっていいと思います。
それでは、なぜこのようなことになるのか、これから詳しく解説させていただきます。
フィボナッチ数列の母関数
まず、母関数とは何かについて説明します。
母関数とは、ある数列の情報を所有している元となる関数です。
たとえば、ここに関数F(x)が存在するとして、このxに1を代入した場合、その結果が、今テーマとしている数列の和とぴったり同じ結果になるというものです。
なので、関数f(x)のxに1を代入することで、今テーマとしている数列和と同じ数式になるものであれば、母関数とすることができます。
そのため、母関数はある数列の情報を持ちつつ、そこから拡張された関数、ととらえることもできます。
一般的には、母関数として次のようなべき級数の関数を定義することが多いです。
\(f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+\cdots=\sum_{n=0}^{∞}a_nx^n\)
さて、フィボナッチ数列の母関数ですが、
このような関数を定義したとします。
\(初期値:a_0=0 a_1=1\)
\(a_{n+2}=a_n+a_{n+1} (n\geq0) \)
\(F(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5+\cdots\) ③
ここに、x=1を代入すれば、フィボナッチの数列の無限和になることをご確認いただければと思います。
この③の式の左右にxをかけると、以下のような式が出来あがります。
\(F(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5+\cdots\) ④
\(xF(x)=a_0x+a_1x^2+a_2x^3+a_3x^4+a_4x^5+a_5x^6+\cdots\) ⑤
\(x^2F(x)=a_0x^2+a_1x^3+a_2x^4+a_3x^5+a_4x^6+a_5x^7+\cdots\) ⑥
ここで、式をさらに一般化するために、④-⑤-⑥と引き算します。
フィボナッチ数列の漸化式である\(a_{n+2}=a_n+a_{n+1}\)より\(a_{n+2}-a_{n+1}-a_n=0\)が成立しますので、この式の右辺はほとんど消えます。
すると、右辺がスッキリします。
④-⑤-⑥の計算結果は、
\(F(x)(1-x-x^2)= a_0 + a_1x – a_0x = a_0 + (a_1 – a_0)x =x\)となり、次のような結果になります。
$$F(x)=\frac{x}{1-x-x^2}$$
$$ -\frac{\sqrt{5}-1}{2}<x<\frac{\sqrt{5}-1}{2} $$
これが、フィボナッチ数列の母関数です。
ただし、このままF(x)のxに1を代入することは間違いです。なぜなら、xの収束半径が1より小さい値だからで、x=1だと定義域から外れてしまうからです。
解析接続
それでは、ここから解析接続された関数を紹介致します。
それは、先ほどのF(x)をF(z)と、複素関数にまで拡張することです。
$$F(z)=\frac{z}{1-z-z^2}$$
これは、ただxを複素数のzにまで拡張したものです。
ここで、F(z)は\(1-z-z^2=0\)の場合を除いて、微分可能です。
ここの\(1-z-z^2=0\)の条件の場合、微分不可能となっています。このような点を複素関数の分野では孤立特異点といいます。なので、定義域外といえます。
複素関数で定義域内の全ての点で微分可能な関数を、正則関数といいます。
このF(z)も定義域内では立派な正則関数です。
解析接続とは、元々の関数の定義域内での値が同じである条件を保ちつつ、定義域外まで拡張された関数のことです。要はF(x)で定義されていなかった定義域外の部分まで、なめらかな曲面でつないで拡張して、定義してしまおうというもの。
数学とは、式を拡張することで発展してきた経緯があるので、その一環として実数から複素数まで拡張すると、新しい世界が開けてきます。
なぜ実数ではだめだった領域にまで、複素数であれば関数が拡張が可能かという理由については次のようなイメージです。
無限大にそびえる山を実数軸の直線でまっすぐ進むと無限大の壁にぶち当たり、それ以上は定義域の外になります。
しかし、山のふもとをぐるっと回って迂回すれば、無限大の山を登らなくても、先に進めてしまいます。しかも、なめらかな曲面で繋がっています。
なので、解析接続で複素数まで拡張すると、実数では不可能だった領域まで、関数を定義することができてしまいます。
また、その際に元の関数の定義域内や接続面で微分可能である条件が必要となっており、正則関数であることが条件となっています。
そのため、上記の関数は解析接続の条件を満たしているといえます。
そこで、解析接続によって拡張されたこの関数は、ここではじめて元のF(x)の定義域が拡張され、拡張されたがゆえにz=1と代入することができるのです。
なので、本来定義域の外だった関数を、解析接続によって拡張した部分で1という数字を代入しているので、元のフィボナッチ数列の式の結果と異なるのは、当然起こりうることだといえましょう。
フィボナッチ数列が-1とイコールで結ばれたものは、解析接続されたこのF(1)の結果なのであって、解析接続されてない状態の通常の結果は発散しますので、この違いを理解しておきましょう。
フィボナッチ数列の無限和が-1になる従来の証明方法
ここで、いわゆるフィボナッチ数列の無限和が-1になるとされる、従来の証明方法のひとつで、解析接続を使わない簡単なものをご案内致します。
なお、ここから先の証明方法は 教える方の中には 厳密な証明とはいえない、と但し書きを沿える方もいらっしゃいます。また、そのような但し書きを添えずに普通に証明のひとつとして解説される方もいらっしゃいます。
それでは、その証明方法を解説致します。
フィボナッチ数列の無限和は定義式より、次のように示されることは先ほどお伝えしました。
S=0+1+1+2+3+5+8+13+…
ここで、0を消去して1つ分だけズラしたものをこの式の下に書きます。
そして、これらの2つ式の和を求めます。
S=0+1+1+2+3+5+8 +13+…
S=1+1+2+3+5+8+13+…
すると、以下の通りになります。
2S=1+2+3+5+8+13+…
この式の右辺はフィボナッチ数列から1だけ少ないので先頭に-1+1を足し合わせると…
\(\eqalign{2S&=-1+1 +1+2+3+5+8+13+\cdots\cr&=-1+(1+1+2+3+5+8+13+\cdots)\cr&=-1+S}\)
\(∴S=-1\)
これが、フィボナッチ数列の無限和が-1になる証明方法のひとつとして、ネット上で紹介されているものです。
フィボナッチ数列の無限和が-1になる解析接続を使わない証明方法の間違い
ここから後は、先ほど示しました解析接続を使わない従来の証明方法が誤っているとする、私個人の自説を紹介したいと思います。
今から導き出す証明方法は、世の中で知られている既存の説ではありませんので、もし誤り等がございましたら、コメント欄にてご指摘いただけますと幸いです。
また、もしかすれば数学的には、解析接続を使わない証明方法が既に間違いであることとして、以前から専門家の方によって指摘されている可能性もあります。ただし、ここで紹介するその根拠については、まだ世の中に公表されてない可能性がありますので、ここで発表させていただく意義があると思っています。
さて、このフィボナッチ数列の無限和が-1になる、解析接続を使わない証明方法について、私は果たして正しい証明方法なのだろうかと思っています。
その根拠は、無限大に発散する、数列の無限和の式をひとつズラして足し算している点です。
この式のように、上側のほうは下側に対して一つ分だけ右にズレています。ここが私個人としてはおかしいと思えるところです。
S=0+1+1+2+3+5+8 +13+…
S=1+1+2+3+5+8+13+…
たとえば、そのおかしいと思える点をわかりやすくいえば、次の無限数列の和があったとします。
S=1+1+1+1+1+1+1+…
この数列をコピーして、1つ右にズラして足し算してみましょう。
S=1+1+1+1+1+1+1+…
S=0+1+1+1+1+1+1+1+…
結果は次の通りです。
2S=1+2+2+2+2+2+2+…
なので、次のような形に至ります。
2S=1+2(1+1+1+1+1+…)
2S=1+2S
2S=1+2S?あれ、おかしいと思いませんか?左辺と右辺が同じでありません。
左辺と右辺が違うものを等号で結ぶのは、論理的に誤っている証拠だと私には思えるのです。
さらに、次の数列があったとしましょう。
S=1+2+3+4+5+…
これをコピーして、右にひとつずらしたものを、今度は引き算します。
S=1+2+3+4+5+…
S= 1+2+3+4+5+…
0=1+1+1+1+1+1+…
おかしいですね。1の無限和が0になっています。こんなことはありえないはずです。
なので、私としては無限大に発散する定数の数列による式の足し算、引き算では証明にならないケースがあると思っています。
なお、数列の式をコピーして右にずらして引き算することは 数学ではよくあることで、たとえば無限和が収束したり、関数で綺麗にまとめることができたりする場合であれば十分成立することがほとんどだと思います。
おそらく、数列が関数形式、あるいは定数形式であっても、数列の和が無限大に発散しない条件であれば、式をズラしても問題ないと思われます。
しかし、問題は数列の和が無限大にまで発散する定数の数列の場合です。
変数ではない、このような定数による数列の無限和が無限大に発散する場合は、右に1つずらして足し算やら引き算をする方法では証明にならないのではないかと個人的に思っています。
この証明方法はリーマンゼータ関数の無限和においても同じことがいえると思います。それにつきましては、機会がありましたら改めて解説させていただきます。
この方法に対して、厳密な証明とはいえない証明、と但し書きを沿えるかたもいらっしゃいますが、たとえ厳密でなくとも この方法自体が証明方法として成立しない可能性があります。
どこまでの条件が証明として正しいものになり、どこまでの条件が証明にならないのか、その詳細な部分につきましては今後のテーマとしたいと思います。
これが、従来の証明方法が間違っているのではないか、という私個人の根拠です。
サイエンススタジオ Youtubeチャンネル